はじめに
生成AI技術の進化は目覚ましく、ビジネスのあらゆる側面でその影響が顕在化しています。業務効率化、新たな顧客体験の創出、データ分析の高度化など、生成AIがもたらす変革は計り知れません。しかし、その急速な発展ゆえに、「どのように導入すれば良いのか」「具体的な活用方法が分からない」といった課題に直面する企業も少なくありません。特に、複数のプロダクトを展開する企業においては、個々のプロダクトに生成AIを組み込むだけでなく、全体として一貫性のある、スケーラブルな基盤をどのように設計するかが重要な経営課題となっています。
こうした背景の中、生成AIの最前線で活躍する企業が具体的な知見を共有するイベントは、多くのビジネスパーソンにとって貴重な学びの機会となります。本記事では、2025年11月13日に開催される「Loglass AI TALK #6 生成AI時代のマルチプロダクト基盤設計」に焦点を当て、その内容と参加する意義について深掘りして解説します。
Loglass AI TALK #6 の概要
株式会社ログラスが主催する「Loglass AI TALK #6 生成AI時代のマルチプロダクト基盤設計」は、生成AIのビジネス活用における最先端の議論が交わされる注目のイベントです。ニュース記事でも「ログラスは、同社主催によるイベント「Loglass AI TALK」の第6回目となる、「生成AI時代のマルチプロダクト基盤設計」を11月13日19時〜21時に同社オフィス(東京都港区)にて開催する。参加費は無料で、事前登録が必要。」と紹介されており、その重要性が伺えます。
- イベント名: Loglass AI TALK #6 生成AI時代のマルチプロダクト基盤設計
- 開催日時: 2025年11月13日(水) 19:00 〜 21:00
- 場所: 株式会社ログラス オフィス (東京都港区芝5-13-15 芝三田森ビル2F)
- 参加費: 無料
- 主催: 株式会社ログラス
- イベント詳細・参加登録: https://loglass.connpass.com/event/300407/
このイベントは、生成AIをマルチプロダクト環境にどのように統合し、ビジネス価値を最大化するかという、現代の企業が直面する最も複雑な課題の一つに光を当てます。参加費は無料で、事前登録が必要となるため、興味のある方は早めに申し込みを済ませることをお勧めします。
イベントのテーマ:生成AI時代のマルチプロダクト基盤設計
生成AIの導入は、単一のプロダクトに限定されるものではありません。多くの企業が複数のSaaSプロダクトやサービスを提供しており、それぞれのプロダクトにAI機能を組み込むことで、顧客体験の向上や業務効率化を図ろうとしています。しかし、個別にAIを導入するだけでは、以下のような課題が生じかねません。
- 一貫性の欠如: 各プロダクトで異なるAIモデルやツールを使用すると、ユーザー体験やデータ連携に一貫性がなくなり、全体のブランドイメージや効率性が損なわれる可能性があります。
- 開発・運用コストの増大: 個別のAI機能を開発・運用することは、リソースの重複や非効率を生み出し、コストを増大させます。
- スケーラビリティの課題: 各プロダクトの成長に合わせてAI機能をスケールさせる際、統一された基盤がないと技術的なボトルネックが生じやすくなります。
- ガバナンスとリスク管理: AIの倫理的利用、データプライバシー、セキュリティといった側面において、全体的なガバナンス体制の構築が困難になります。
このような課題を解決するためには、マルチプロダクト全体を見据えた生成AI基盤の設計が不可欠です。本イベントのテーマである「生成AI時代のマルチプロダクト基盤設計」は、まさにこの中心的な課題に焦点を当てています。共通のAI基盤を構築することで、開発効率の向上、一貫したユーザー体験の提供、運用コストの削減、そして強固なガバナンス体制の確立を目指します。これは、現代のSaaS企業やテクノロジー企業が持続的に成長し、競争優位性を確立するための重要な戦略となるでしょう。
生成AIの倫理とガバナンスについては、過去記事「【イベント】生成AI倫理とガバナンス:2025/11/15開催:責任あるAI利用を学ぶ」でも詳細に解説していますので、併せてご参照ください。
豪華登壇者とそれぞれの視点
本イベントの最大の魅力は、日本を代表するSaaS企業やFinTech企業から、生成AIの最前線で活躍するエキスパートが登壇することです。各登壇者が、それぞれの企業の立場から、マルチプロダクトにおける生成AI基盤設計の課題と解決策について議論を深めます。
株式会社LayerX 執行役員CTO 松本 勇気 氏
株式会社LayerXは、FinTech領域で「バクラク」シリーズを展開し、BtoB SaaS市場で急成長を遂げています。松本氏は、LayerXの技術戦略を牽引する人物であり、過去にも生成AIの「戦力化」に関するセミナーで登壇経験があります(【イベント】生成AI「戦力化」セミナー:LayerX松本CTO登壇、11/11開催)。
LayerXのような複数のプロダクトを持つ企業が、どのように生成AIを事業横断的に活用し、各プロダクトの価値を高めているのか、その具体的な戦略や技術的なアプローチが共有されることが期待されます。特に、金融という厳格な規制が伴う領域でのAI導入は、セキュリティや信頼性といった側面で高度な設計が求められます。松本氏からは、そうした複雑な環境下での基盤設計のベストプラクティスや、組織としてAIをどのように位置づけ、開発体制を構築しているかといった、実践的な知見が得られるでしょう。
株式会社SmartHR プロダクト開発グループ エンジニアリングマネージャー 吉田 圭佑 氏
株式会社SmartHRは、人事・労務SaaSのリーディングカンパニーとして、日本の多くの企業で利用されています。大規模なユーザーベースと多様な機能を持つSmartHRにおいて、生成AIをどのように導入し、既存のプロダクト群とシームレスに連携させるかは、非常に複雑な課題です。
吉田氏からは、人事領域という機密性の高いデータを扱うSaaSにおいて、生成AIの活用におけるデータプライバシーやセキュリティへの配慮、そしてユーザー体験を損なわずに新しい価値を提供するための基盤設計について語られることが予想されます。特に、大規模プロダクトにおけるAI機能の追加や改善を、いかに効率的かつ安定的に行っていくかという運用面での知見は、多くの企業にとって参考になるはずです。
株式会社ログラス 執行役員 CTO 岩瀬 義則 氏
本イベントの主催である株式会社ログラスは、経営管理SaaS「Loglass」を提供し、企業の経営計画や予実管理を支援しています。ログラス自体も、生成AIの活用を通じて、経営管理業務の効率化や高度化を目指している企業です。
岩瀬氏からは、主催企業としての生成AIへのビジョンや、自社プロダクトにおける生成AIの導入事例、そして今後のマルチプロダクト戦略におけるAI基盤の重要性について語られるでしょう。特に、経営管理というデータドリブンな領域で生成AIがどのような価値を生み出し、そのための技術基盤がどのように設計されているのかは、参加者にとって具体的なヒントとなるはずです。
これら3社の登壇者が、それぞれの業界やプロダクトの特性を踏まえながら、生成AI時代のマルチプロダクト基盤設計について議論することで、多角的かつ実践的な視点が得られることが期待されます。単なる技術論に留まらず、ビジネス戦略や組織体制、倫理的側面まで含めた包括的な議論が展開されるでしょう。
本イベントから得られる学びと参加のメリット
「Loglass AI TALK #6」に参加することで、参加者は以下のような具体的な学びやメリットを得ることができます。
- 実践的な基盤設計の知見: マルチプロダクト企業が生成AIを導入する際に直面する具体的な課題と、それを解決するための基盤設計のベストプラクティスを学ぶことができます。理論だけでなく、各社の実践例から具体的なヒントが得られるでしょう。
- 業界トップランナーの戦略: LayerX、SmartHR、ログラスといった、それぞれの業界で生成AI活用をリードする企業のCTOやエンジニアリングマネージャーが、どのようなAI戦略を描き、それを技術的にどう実現しているのかを直接聞くことができます。
- データプライバシーとセキュリティへの配慮: 機密性の高いデータを扱うSaaS企業が、生成AI活用においてデータプライバシーやセキュリティをどのように確保しているか、その具体的なアプローチやガバナンス体制について理解を深めることができます。
- 組織体制と文化の構築: 生成AIを効果的に導入・運用するために、どのような組織体制が必要か、エンジニアリングチームやプロダクトチームがどのように連携すべきかといった、組織論や文化に関する示唆も得られる可能性があります。
- ネットワーキングの機会: 参加者同士や登壇者との交流を通じて、生成AIに関する最新情報を交換し、新たなビジネスチャンスやパートナーシップを見つける機会にもなり得ます。
生成AIの導入は、単に最新技術を導入するだけでなく、企業の事業戦略や組織文化全体に影響を与えるものです。本イベントでは、そうした多角的な視点から生成AIの基盤設計について深く掘り下げることができ、参加者のビジネスにおける生成AI活用を加速させる貴重な機会となるでしょう。
生成AIの戦略と導入ロードマップに関する情報は、過去記事「【イベント】生成AI戦略と導入ロードマップセミナー:2025/12/10開催」でも詳しく解説しています。
参加を検討すべきターゲット層
本イベントは、特に以下のような方々に強くお勧めします。
- プロダクトマネージャー (PdM): 複数のプロダクトに生成AI機能を組み込み、プロダクト体験を向上させたいと考えている方。AI機能の企画・開発における課題解決のヒントが得られます。
- ソフトウェアエンジニア・開発者: 生成AIモデルの選定、API連携、スケーラブルなインフラ構築など、技術的な側面からマルチプロダクト基盤設計に関心がある方。
- CTO・VPoE・技術責任者: 企業の技術戦略として生成AIの導入を検討しており、組織全体のAI基盤設計や開発体制構築の知見を求めている方。
- AI戦略担当者・DX推進担当者: 生成AIを事業成長のドライバーとして位置づけ、具体的な導入ロードマップや活用戦略を策定したい方。
- 事業責任者・経営層: 生成AIが自社のビジネスにどのような影響を与え、どのような投資が必要になるのか、その全体像を把握したい方。
生成AIの活用は、もはや一部の技術者だけのテーマではありません。企業の競争力を左右する重要な要素となっており、異なる職種や立場の人々が連携して取り組む必要があります。本イベントは、そうした多様なステークホルダーが共通の認識を持ち、具体的な行動へと移すための土台を築く上で非常に有益な機会となるでしょう。
まとめ
2025年11月13日に開催される「Loglass AI TALK #6 生成AI時代のマルチプロダクト基盤設計」は、生成AIのビジネス活用を深く理解し、実践するための貴重なイベントです。LayerX、SmartHR、ログラスといった業界のトップランナーが登壇し、マルチプロダクト環境における生成AI導入の課題、その解決策としての基盤設計、そして各社の具体的なアプローチについて議論を交わします。
生成AIの急速な進化は、企業に新たな機会と同時に複雑な課題をもたらしています。特に、複数のプロダクトを持つ企業にとって、一貫性があり、スケーラブルで、かつ安全なAI基盤を設計することは、今後の成長戦略において不可欠です。本イベントは、そのための実践的な知見と具体的なヒントを提供し、参加者の皆様が生成AIを活用してビジネスを次のステージへと進めるための強力な一歩となるでしょう。
生成AIの技術変革とビジネスへの応用事例については、過去記事「【イベント】生成AIの技術変革とビジネス:7/3開催:最新動向と応用事例を解説」も参考になるはずです。この機会を逃さず、ぜひイベントに参加し、生成AI時代のビジネスをリードする知見を獲得してください。

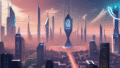

コメント