生成AIに関する展示会やセミナーが数多く開催されるようになりました。最新の技術動向や活用事例に触れることができる貴重な機会であり、参加するだけでも多くの刺激を受けることでしょう。
しかし、イベントに参加して「良い話を聞いた」「勉強になった」で終わってしまっては、その価値を最大限に引き出したとは言えません。本当に重要なのは、イベントで得た知識やインスピレーションを、いかにして自社のビジネスや日々の業務に落とし込み、具体的な成果へと繋げるかです。
今回は、生成AIイベントで得た学びを「宝の持ち腐れ」にしないための、具体的な3つのステップをご紹介します。
ステップ1:情報の「自分ごと化」と再構築
イベントでは、最先端の事例や専門的な技術解説など、多岐にわたる情報がシャワーのように降り注ぎます。そのすべてを記憶し、持ち帰るのは不可能です。大切なのは、受け取った情報を自分や自社の置かれている状況に引きつけて再解釈する「自分ごと化」のプロセスです。
例えば、ある企業の「顧客対応業務をAIで自動化した事例」を聞いたとします。単に「すごい事例だった」とメモするのではなく、次のように思考を巡らせてみましょう。
- 「この仕組みは、うちの部署の〇〇という問い合わせ対応に応用できないか?」
- 「全面的な自動化は難しくても、回答文案の作成補助としてならすぐに導入できるかもしれない」
- 「事例で使われていたツールの代わりに、現在社内で利用しているMicrosoft Copilotで同様のことは実現可能か?」
このように、得た情報を自社の課題やリソースと結びつけて具体的に検討することで、単なる知識が「実行可能なアクションプランの種」へと変わります。
ステップ2:スモールスタートで「試す」文化を醸成する
イベントで得たアイデアを元に、いきなり大規模なプロジェクトや予算申請を計画するのは現実的ではありません。多くの場合、企画倒れに終わってしまうでしょう。重要なのは、小さく、素早く試す「スモールスタート」です。
まずは、自分自身やチーム単位で、無料で使えるツールや既存の環境を活用してPoC(Proof of Concept:概念実証)を行ってみましょう。例えば、資料作成の効率化に興味を持ったなら、資料作成AI「Gamma」のようなツールを試してみる。あるいは、ChatGPTだけじゃない!用途別AIツール連携で業務効率を最大化する実践術で紹介されているようなツールを組み合わせて、特定の業務フローを改善できないか実験してみるのです。
「実際にやってみたら、週次の報告書作成時間が平均で30分短縮できた」といった具体的な小さな成功体験は、上司や他部署を巻き込む際の何より強力な説得材料となります。
ステップ3:社内の「伝道師」として情報を共有し、仲間を作る
せっかく得た知識やスモールスタートで得られた知見を、自分だけのものにしておくのは非常にもったいないことです。あなたがイベントで得た熱量を、社内に伝播させる「伝道師(エバンジェリスト)」の役割を担いましょう。
大掛かりな報告会を開く必要はありません。チームの定例会議で5分だけ時間を貰って共有する、社内のチャットツールで「こんな便利な使い方を見つけました」と発信するなど、手軽な方法で十分です。重要なのは、発信を続けることです。
あなたの発信に興味を持つ人が現れれば、その人が次の仲間になります。一人で推進するよりも、二人、三人と仲間が増えることで、取り組みは加速し、やがて組織全体のムーブメントへと繋がっていきます。これは、生成AI時代の「スキル格差」を乗り越える人材育成戦略の観点からも非常に有効なアプローチです。
まとめ
生成AIイベントへの参加は、それ自体が目的ではありません。それは、自社のビジネスを次のステージに進めるための「スタートライン」に立つ行為です。インプットした情報を、いかにして具体的なアクションと成果(アウトプット)に繋げられるか。今回ご紹介した3つのステップを参考に、ぜひイベントでの学びを日々の業務変革に活かしてみてください。

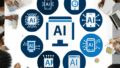
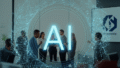
コメント