はじめに
2025年現在、生成AIはビジネスのあらゆる領域でその可能性を広げ、企業の競争力強化に不可欠なテクノロジーとして認識されています。テキスト生成、画像生成、コード生成、データ分析支援など、多岐にわたるタスクの効率化と新たな価値創造に貢献していますが、その急速な普及と進化は、同時に新たな法的リスクの課題も提起しています。著作権侵害、個人情報保護、機密情報漏洩、ハルシネーション(誤情報の生成)など、生成AIの利用に伴う法的・倫理的な問題は、企業にとって喫緊の課題となっています。
このような背景の中、企業が生成AIを安全かつ効果的に導入・活用するためには、潜在的な法的リスクを正確に理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。本記事では、来る2025年12月15日(月)に開催される「生成AIの導入・利用にあたっての法的リスクと対策」と題したセミナーに注目し、その内容を深掘りしながら、企業が生成AI時代を生き抜くために知っておくべき法的論点と実践的な対策について解説します。
イベント概要:生成AIの法的リスクと対策セミナー
今回ご紹介するセミナーは、生成AIのビジネス活用における法的リスクに特化した内容で、企業が直面しうる具体的な課題とその対策について深く掘り下げます。
- イベント名: 生成AIの導入・利用にあたっての法的リスクと対策
- 開催日時: 2025年12月15日(月) 13:00-16:00
- 開催形式: オンライン
- 主催: 株式会社新社会システム総合研究所
- 講師: 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 パートナー弁護士 高瀬 亜富氏
- 詳細情報: 株式会社 新社会システム総合研究所のプレスリリース
このセミナーは、生成AIの導入を検討している企業、すでに活用を進めている企業、またはAI関連の法務・コンプライアンス担当者にとって、非常に実践的な情報提供の場となるでしょう。生成AIがもたらすビジネス変革の波に乗るためには、法的リスクを適切に管理し、安心して技術を活用できる環境を整備することが不可欠です。
生成AIの法的リスク、なぜ今重要なのか
生成AIは、その強力な情報生成能力ゆえに、既存の法制度や社会規範との間で新たな摩擦を生じさせています。特に、企業活動においては、以下のような法的リスクが顕在化しており、その対策が急務となっています。
- 知的財産権侵害: 生成AIが学習したデータに含まれる著作物や、生成されたコンテンツが既存の著作物に類似する場合の法的責任。
- 個人情報保護・機密情報漏洩: プロンプトに含んだ個人情報や企業秘密がAIモデルを通じて外部に漏洩するリスク、または生成されたコンテンツに意図せず機密情報が含まれるリスク。
- ハルシネーション(誤情報生成): AIが事実と異なる情報を生成し、それがビジネス上の意思決定や顧客への情報提供に利用された場合に生じる損害賠償責任や信頼失墜のリスク。
- 差別・不公平な出力: AIモデルの学習データに偏りがある場合、差別的または不公平なコンテンツが生成され、倫理的・法的問題に発展するリスク。
- 利用規約違反: 各生成AIサービスの利用規約を遵守せず、意図しない形でサービスが停止されたり、法的措置を講じられたりするリスク。
これらのリスクは、企業が生成AIを導入する上で避けて通れない課題であり、適切な対策を講じなければ、事業継続に深刻な影響を及ぼす可能性があります。実際、情報セキュリティに関するリスクの高まりは広く認識されており、例えば、株式会社UPFは「生成AIツールの業務利用に潜む情報セキュリティリスクと、その実務的な対応策をテーマとした無料オンラインセミナー」を開催するなど、この分野への関心の高さが伺えます。企業は、生成AIの利便性だけでなく、それに伴う潜在的なリスクにも目を向け、積極的に知識を習得していく必要があります。(参照: 生成AI時代の情報セキュリティ―AIツールにおけるリスクと実務対応を解説するオンラインセミナーを開催 | 株式会社UPFのプレスリリース)
生成AIの技術進化が加速する中、企業は常に最新の法的動向を把握し、自社のAI利用ポリシーをアップデートしていく柔軟性が求められます。法的な問題は、企業のブランドイメージや財務状況に直接的な影響を与えるため、経営層から現場の従業員まで、組織全体で意識を高めることが重要です。
セミナーで深掘りされる主要テーマ
本セミナーでは、高瀬亜富弁護士の専門的な知見に基づき、生成AIの導入・利用にあたって企業が直面する具体的な法的リスクとその対策が包括的に解説されると期待されます。プレスリリースに示されているキーワードから、以下の主要テーマが深く掘り下げられると推測されます。
データ流出と個人情報保護
生成AIの利用において、プロンプトとして入力された情報が、意図せず学習データとして利用されたり、他のユーザーの出力に影響を与えたりするリスクがあります。特に、企業が保有する機密情報や顧客の個人情報を扱う場合、データ流出は重大なインシデントに繋がりかねません。セミナーでは、情報管理のベストプラクティス、個人情報保護法やGDPRなどの規制遵守、そしてリスクを最小限に抑えるための技術的・運用的な対策について解説されるでしょう。具体的には、AI利用におけるプロンプト設計の注意点、AIモデルの選定基準、データマスキングや匿名化の重要性などが議論される可能性があります。
関連するリスク管理については、過去記事「【イベント】生成AIとデータプライバシー:2025/12/20開催:法的要件と技術的対策を解説」でも詳しく解説しています。
知的財産侵害
生成AIが生成するコンテンツの著作権帰属や、学習データに含まれる著作物の利用に関する問題は、AI法務の中でも特に複雑な領域です。生成AIが既存の著作物に酷似したコンテンツを生成した場合、その責任は誰が負うのか、企業はどのような対策を講じるべきか。セミナーでは、著作権法におけるAI生成物の取り扱い、学習データの適法性、そして万が一侵害が発生した場合の対応策などが詳細に説明されることが予想されます。特に、企業が生成AIを用いてマーケティングコンテンツや製品デザインを制作する際に注意すべき点が強調されるでしょう。
ハルシネーション(誤情報)と責任の所在
生成AIは時に、事実に基づかない、もっともらしい「誤情報(ハルシネーション)」を生成することがあります。この誤情報がビジネス上の重要な判断や顧客向けの情報発信に利用された場合、企業の信頼失墜や損害賠償責任に発展する可能性があります。セミナーでは、ハルシネーションのリスクを低減するためのプロンプトエンジニアリングの工夫、生成AIの出力をファクトチェックする体制の構築、そして誤情報による損害発生時の法的責任の所在について、具体的な事例を交えながら解説されることが期待されます。
学習データの適法性と生成モデルのコンプライアンス
生成AIモデルの性能は、その学習データの質と量に大きく依存します。しかし、学習データの収集・利用方法が適法であるかどうかが問われるケースも少なくありません。セミナーでは、ウェブスクレイピングの適法性、データセットのライセンス、そしてAIモデルの透明性(説明可能性)や公平性といった倫理的・法的要件が議論されるでしょう。生成AIの「ブラックボックス性」が問題となる中で、企業はどのようにしてモデルの信頼性とコンプライアンスを確保すべきか、その指針が示されると予想されます。
内部統制と業務効率化
生成AIを企業内で安全に利用するためには、適切な内部統制の構築が不可欠です。セミナーでは、生成AI利用に関する社内ポリシーの策定、従業員へのガイドライン提示と教育、利用状況のモニタリング体制の構築など、実務的な内部統制のあり方が解説されるでしょう。同時に、法的リスクを適切に管理しながら、いかに生成AIの導入によって業務効率化と生産性向上を実現するか、そのバランスの取り方も重要なテーマとなります。リスクを過度に恐れることなく、しかし慎重に、生成AIの恩恵を最大限に引き出すための戦略が提示されると期待されます。
AIの倫理とガバナンスについては、過去記事「【イベント】生成AI倫理とガバナンス:2025/11/15開催:責任あるAI利用を学ぶ」でも詳しく議論されています。
講師「高瀬 亜富氏」の専門性と期待される知見
本セミナーの講師を務めるのは、弁護士法人内田・鮫島法律事務所のパートナー弁護士である高瀬 亜富氏です。内田・鮫島法律事務所は、IT、知財、ベンチャー支援に強みを持つことで知られており、高瀬弁護士も特にIT・AI関連法務、知的財産法務において豊富な経験と実績をお持ちです。
高瀬弁護士の専門性は、生成AIがもたらす複雑な法的課題を多角的に分析し、企業にとって実践的かつ具体的な対策を提示する上で非常に重要です。単なる法解釈にとどまらず、最新の技術動向やビジネス実態を踏まえた上で、企業が現実的に取り組むべきリスク管理のポイントや、契約実務における注意点など、具体的なアドバイスが期待できるでしょう。特に、ベンチャー企業支援の経験から、新しい技術を積極的に活用しようとする企業が陥りやすい落とし穴や、スタートアップが成長段階で直面する法的課題についても深い洞察を提供してくれるはずです。
このような専門家によるセミナーは、インターネット上にあふれる断片的な情報だけでは得られない、体系的かつ信頼性の高い知識を提供します。企業が生成AIを「攻め」のツールとして活用しつつ、「守り」の体制を万全にするための羅針盤となることでしょう。
企業が今、生成AIの法的リスクにどう向き合うべきか
生成AIの導入は、もはや企業の競争戦略において避けて通れない道となっています。しかし、その恩恵を最大限に享受するためには、潜在的な法的リスクを適切に管理し、安心して技術を活用できる環境を整備することが不可欠です。本セミナーは、企業が生成AI時代における法的リスクに効果的に向き合うための貴重な機会を提供します。
セミナーへの参加を通じて、企業は以下の具体的なメリットを得られるでしょう。
- 最新の法的動向の把握: 生成AIに関する法規制は急速に変化しており、常に最新の情報をキャッチアップすることが重要です。本セミナーでは、高瀬弁護士から現状と今後の展望について、専門的な見地からの解説が期待できます。
- 具体的なリスクの特定と対策: 抽象的なリスク論ではなく、著作権侵害、データ漏洩、ハルシネーションなど、企業が直面しうる具体的な法的リスクとその実践的な対策について学ぶことができます。
- 社内ガバナンス体制の構築支援: 生成AIの利用に関する社内ガイドラインの策定、従業員への教育、監視体制の構築など、実効性のある内部統制を整備するためのヒントが得られます。
- 信頼できる専門家からの知見: 経験豊富な弁護士による解説は、インターネット上の情報だけでは得られない深い洞察と信頼性を提供します。
生成AIの導入は、単にツールを導入するだけでなく、企業の文化、業務プロセス、そしてリスク管理体制全体を見直す機会でもあります。法的リスクを適切に管理することは、企業の持続的な成長と社会からの信頼を確保するために不可欠です。本セミナーは、そのための第一歩となるでしょう。
セキュリティ対策やリスク評価に関する過去記事もご参照ください。
まとめ
生成AIは、企業に計り知れない可能性をもたらす一方で、法的リスクという新たな課題を突きつけています。2025年12月15日(月)に開催される「生成AIの導入・利用にあたっての法的リスクと対策」セミナーは、この複雑な課題に企業がどのように向き合うべきか、具体的な指針と実践的な対策を提供する貴重な機会です。
知的財産侵害、データ流出、誤情報のリスクなど、多岐にわたる法的論点について、専門家である高瀬亜富弁護士の知見を得ることで、企業は生成AIをより安全かつ戦略的に活用するための基盤を築くことができるでしょう。生成AIの技術が進化し続ける中、企業は常に法的・倫理的な側面への意識を高め、適切なガバナンス体制を構築していくことが、持続的な成長と社会からの信頼獲得に繋がります。本セミナーへの参加は、生成AI時代をリードする企業にとって、必要不可欠な投資となるはずです。

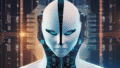
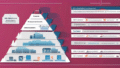
コメント