はじめに
2025年、生成AIはビジネスのあらゆる領域に浸透し、企業の競争力向上に不可欠なツールとなりつつあります。しかし、その急速な普及と利便性の裏側で、情報漏洩リスクやハルシネーション(誤情報生成)といった潜在的な課題が浮上しています。特に企業や行政機関では、機密情報や個人情報の取り扱いが厳格に求められるため、これらのリスクにいかに対応するかが喫緊の課題となっています。
本稿では、企業・組織が生成AIを安全かつ効果的に活用するための戦略、特に情報漏洩リスク回避に焦点を当て、独自開発AI、セキュアな生成AIサービス、そしてRetrieval-Augmented Generation (RAG)といった最新のアプローチを深掘りし、その具体的な事例と導入のメリットについて議論します。
生成AI利用における情報漏洩リスクの現状と課題
生成AIの利用が拡大するにつれて、企業は新たなリスクに直面しています。最も懸念されるのは、社員が業務で生成AIを使用する際に、意図せず機密情報や個人情報を入力してしまうことです。汎用的なクラウドベースの生成AIサービスでは、入力されたデータがモデルの学習に利用されたり、他のユーザーの応答に影響を与えたりする可能性が指摘されており、これが情報漏洩のリスクにつながります。たとえデータが学習に利用されないと謳われていても、外部サービスに機密データを送信すること自体が、企業のセキュリティポリシー上問題となるケースが少なくありません。
また、生成AI特有の課題としてハルシネーション(Hallucination)、すなわちAIが事実に基づかない、もっともらしい虚偽の情報を生成する問題も挙げられます。これにより、誤った情報が業務プロセスに取り込まれ、誤った意思決定や顧客への誤案内につながる可能性があります。アスキーの報道(2025年9月26日)では、AIが時々もっともらしい嘘をつくハルシネーションを見破り、ファクトチェックする重要性が解説されています。利用者はAIの出力を鵜呑みにせず、常にその正確性を検証する姿勢が求められます。AIは時々、もっともらしいウソをつく ハルシネーションを見破りファクトチェックする4つの方法(アスキー) – Yahoo!ニュース
Deloitteが2025年9月26日に発表した調査結果(CNET報道)によると、生成AIの利用が急速に普及する一方で、多くの人々がAI自体やその背後にある企業に対する「信頼の欠如」を抱えていることが明らかになりました。この調査では、生成AIが精神衛生問題や依存症を悪化させ、プライバシーを侵害し、常に事実を誤る可能性があるという懸念が示されています。企業が生成AIを導入する際には、技術的なリスク対策だけでなく、社員や顧客からの信頼をどのように構築するかも重要な課題となります。AI Has a Trust Problem. That’s Not Stopping People From Diving In – CNET
このような背景から、企業・組織は生成AIの利便性を享受しつつ、いかにしてこれらのリスクを最小限に抑え、安全な運用環境を構築するかが求められています。
リスク回避のためのアプローチ:独自開発とセキュアなサービス
情報漏洩リスクやハルシネーションといった課題に対し、企業・組織は大きく分けて二つのアプローチで対応を進めています。一つは独自に生成AIシステムを開発・運用すること、もう一つはセキュリティ機能が強化された生成AIサービスを利用することです。
JALの事例に学ぶ独自開発AIの利点
日本航空(JAL)は、情報漏洩リスクを回避する目的で生成AIを独自開発し、社員の8割以上が活用するという驚異的な成果を上げています。au Webポータルの報道(2025年9月27日)によると、JALが独自開発を選んだ最大の理由は、外部の汎用AIサービスを利用する際の情報漏洩リスクを完全に排除することにありました。独自開発により、JALは自社の閉域ネットワーク内でAIを運用し、機密データが外部に流出する可能性を根本から遮断しています。
このアプローチの利点は多岐にわたります。
- 高いセキュリティレベル:自社管理下の環境で運用するため、外部サービスに依存することなく、厳格なセキュリティポリシーを適用できます。
- データガバナンスの強化:入力データや学習データがどのように扱われるかを完全にコントロールでき、情報漏洩のリスクを最小化します。
- 企業文化への最適化:JALの事例のように、自社の業務プロセスや企業文化に合わせたカスタマイズが可能となり、社員がより使いやすいAI環境を提供できます。これにより、社員の利用促進と業務効率化に大きく貢献します。
JALの事例は、情報セキュリティが最優先される企業にとって、独自開発AIが強力な選択肢となり得ることを示しています。JAL、社員8割超が活用の生成AIが衝撃的…情報漏洩リスク回避目的で独自開発|au Webポータル
ただし、独自開発には高度な技術力と多大なコスト、そして運用・保守のための継続的なリソースが必要となります。そのため、すべての企業がこのアプローチを取れるわけではありません。
セキュアな生成AIサービスの登場
独自開発が難しい企業向けには、セキュリティ機能を強化した生成AIサービスが多数登場しています。これらのサービスは、情報漏洩リスクを低減しつつ、生成AIの恩恵を享受できるよう設計されています。
医療DXを推進する「SecuAiGent」
株式会社ユニリタは、2025年10月に開催される「医療DX・IT EXPO【東京】」で、セキュアな生成AIサービス「SecuAiGent(セキュアイジェント)」を出展します(PR TIMES報道)。医療分野では、患者の機密性の高い個人情報や診療データを取り扱うため、情報セキュリティは最も厳しく問われる要素の一つです。SecuAiGentは、こうした医療機関が抱える現場課題の解決を目指し、セキュリティを最優先した設計がなされています。具体的には、データが外部に流出しないような環境構築や、アクセス制御、監査ログ機能などが強化されていると推測されます。これにより、医療従事者は安心して生成AIを業務に活用し、医療DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進できるようになります。セキュアな生成AIで医療DXを推進/「SecuAiGent」、医療DX・IT EXPO【東京】に出展 | 株式会社ユニリタのプレスリリース
関連する過去記事として、生成AIのガバナンスに関するものがあります。企業が生成AIを導入する際のルール作りやリスク管理については、生成AIガバナンス:ラックの策定サービスが企業リスクを低減するの記事もご参照ください。
自治体向けRAG強化サービス「QommonsAI」
自治体向け生成AIサービスでトップシェアを誇る「QommonsAI(コモンズAI)」は、2025年9月26日にver.2.0.5をリリースし、RAG(Retrieval-Augmented Generation)の精度を大幅に向上させました(エキサイトニュース報道)。RAGは、生成AIが回答を生成する際に、事前に与えられた外部の信頼できる情報源(ドキュメント、データベースなど)を参照させる技術です。これにより、AIが学習データにない情報を「創造」して誤情報を生成するハルシネーションのリスクを低減し、かつ最新かつ正確な情報に基づいた回答を生成することが可能になります。
QommonsAIの進化は、特に自治体において重要です。住民からの問い合わせ対応や内部資料作成など、正確性と信頼性が求められる業務において、RAGの強化は大きなメリットをもたらします。
- ハルシネーションの抑制:自治体の条例や規則、公開情報といった信頼性の高いデータソースを参照することで、AIが誤った情報を生成するリスクを大幅に減らします。
- 情報漏洩リスクの低減:自治体内部のローカルデータや閉域ネットワーク内のデータのみをRAGの参照元とすることで、機密情報が外部のAIモデルに学習されることを防ぎます。
- 最新情報の反映:RAGはモデルの再学習なしに、参照する外部データを更新するだけで最新情報に対応できるため、迅速な情報提供が可能です。
このアップデートでは、100MB・CSV対応がなされ、より多様な形式のデータをRAGの参照元として活用できるようになりました。これにより、自治体は手元の膨大なドキュメントを安全かつ効率的にAIに活用させることが可能になります。自治体トップシェアの生成AI【QommonsAI(コモンズAI)】ver.2.0.5をリリース -100MB・CSV対応でRAG精度爆上げ! (2025年9月26日) – エキサイトニュース
RAGの活用は、企業が生成AIを導入する際の「情報漏洩リスクとハルシネーション対策」の最も強力な武器の一つと言えるでしょう。生成AIのプライベートモデルに関するより詳細な情報については、情報漏洩ゼロへ:生成AIプライベートモデル「GAVAGAI Private Model」が拓く企業活用の新常識も参考になります。
国産推論API基盤「さくらのAI Engine」
さくらインターネットが提供する推論API基盤「さくらのAI Engine」の一般提供開始も、情報漏洩リスク回避の観点から注目に値します(CodeZine報道)。国産サービスである点は、データの保管場所や法規制順守において、国内企業にとって大きな安心材料となります。企業が自社データを使って生成AIモデルを構築・運用する際に、国内のセキュアなインフラを利用できることは、情報漏洩リスクを低減し、より安心してAI活用を進めるための基盤となります。さくらインターネット、推論API基盤「さくらのAI Engine」の一般提供を開始
技術的対策と運用上のベストプラクティス
情報漏洩リスクを回避し、生成AIを安全に活用するためには、技術的な対策と同時に、組織全体での運用上のベストプラクティスを確立することが不可欠です。
1. RAG(Retrieval-Augmented Generation)の積極的活用
前述のQommonsAIの事例でも触れたように、RAGはハルシネーションと情報漏洩リスクの両方に対処する上で極めて有効な技術です。企業は、自社のドキュメントやデータベースを外部参照元として設定し、生成AIがその情報に基づいて回答を生成する仕組みを導入すべきです。これにより、AIが外部のインターネット情報を参照することなく、社内情報に基づいた正確な回答を提供できるようになります。これは、企業が「生成AIアプリケーション」を構築する際の基本的なアプローチとなり、従来のアプリケーションとは異なり、バックエンドで生成AIモデルを用いることで新たなコンテンツを生み出すことを可能にします。生成AIアプリケーションとは? 具体例や仕組みを分かりやすく解説
2. プロンプトエンジニアリングの徹底と社員教育
生成AIから求める答えを的確に引き出すためには、適切な「プロンプトのお作法」を知ることが重要です(@DIME報道、2025年9月26日)。これは単に技術的な問題だけでなく、情報漏洩リスクの観点からも重要です。社員が「機密情報を入力しない」というルールを理解するだけでなく、どのような情報をどこまで入力してよいのか、どのようなプロンプトであれば安全に利用できるのかといった具体的なガイドラインを徹底し、繰り返し教育する必要があります。生成AIを正しく使いこなす基本作法を徹底解説!初心者必見のポイントとは(@DIME) – Yahoo!ニュース
株式会社あいプランが社員のAIリテラシー向上を目的とした社内勉強会を初開催した事例(PR TIMES報道、2025年9月26日)は、この重要性を示しています。企業は、業務効率化や新しいサービス開発のために生成AIを導入するだけでなく、社員がAIを安全に使いこなすためのリテラシー教育に投資すべきです。【開催報告】生成AI社内勉強会を初開催 ~AIリテラシー向上に向けた第一歩~ | 株式会社あいプランのプレスリリース
プロンプトの具体的な実践方法については、生成AIを現場で活かす実践プロンプト術:非エンジニアも業務効率を劇的に向上や、非エンジニアのための生成AIプロンプト入門:AIとの対話をスムーズにする設計術も参考になります。
3. 利用ガイドラインの策定とガバナンス
JALの事例のように独自開発AIを導入する場合でも、セキュアなサービスを利用する場合でも、企業は明確な生成AI利用ガイドラインを策定し、組織全体で徹底する必要があります。どのような情報であれば生成AIに入力しても良いのか、生成された情報の確認方法、ハルシネーション発生時の対応、著作権や知的財産権に関する注意点などを明文化することが重要です。これにより、社員は安心してAIを活用できるだけでなく、企業のコンプライアンス体制も強化されます。
生成AIの活用支援を通じて企業変革を実現する株式会社グラファーが「第6回 AI・人工知能EXPO【秋】」へ出展(2025年10月8日~10日)することからも、企業変革におけるAI活用とガバナンスの重要性が伺えます。生成AIの活用支援を通じて企業変革を実現するグラファー、「第6回 AI・人工知能EXPO【秋】」へ出展 | ニコニコニュース
4. AI監査とファクトチェックの重要性
生成AIの出力は、常に人間による監査とファクトチェックが必要です。特に重要な意思決定に関わる情報や、公開される情報については、AIの生成物をそのまま利用するのではなく、必ず人間の目で検証するプロセスを組み込むべきです。これにより、ハルシネーションによる誤情報のリスクを回避し、情報の信頼性を確保します。
今後の展望と課題
2025年、生成AIは企業活動において不可欠な存在となりつつありますが、情報漏洩リスク回避と安全な活用は依然として重要なテーマです。今後は、以下の点が進展していくと予測されます。
- セキュアなAIエコシステムの構築:JALのような独自開発AIだけでなく、SecuAiGentやQommonsAIのように、特定の産業や用途に特化したセキュアな生成AIサービスがさらに多様化し、企業は自社のニーズに合わせた最適なソリューションを選択できるようになるでしょう。また、さくらのAI Engineのような国産のセキュアな基盤サービスも、日本企業のAI活用を後押しします。
- AI倫理と規制の進化:生成AIの普及に伴い、各国政府や国際機関によるAI倫理ガイドラインや法規制の整備がさらに進むと予想されます。企業はこれらの動向を注視し、常に最新の規制に準拠したAI運用体制を構築する必要があります。
- 人材育成と組織文化の変革:生成AIを安全かつ効果的に活用するためには、AIリテラシーの高い人材の育成が不可欠です。また、AIを「道具」として捉え、人間が最終的な責任を持つという組織文化を醸成することも重要です。Forbesの報道(2025年9月27日)では、AIが最も影響を与えるのはその開発者であるIT・ソフトウェア開発職であると指摘されており、ルーティン業務がAIに代替されることで、人間は「作業を行う」から「作業を指示する」役割へとシフトしていく可能性が示唆されています。AI Is Most Likely To Reshape The Jobs Of Its Creators – Forbes これは、全社員がAIとの協業を前提としたスキルとマインドセットを身につける必要があることを示唆しています。
- 継続的な技術革新とリスクマネジメントのバランス:生成AI技術は日進月歩で進化しており、新たな機能が登場するたびに新たなリスクも生まれる可能性があります。企業は、最新の技術動向を常に把握し、リスクマネジメント体制を継続的に見直す必要があります。
生成AIは、企業に計り知れない可能性をもたらす一方で、その利用には慎重なアプローチが求められます。情報漏洩リスクを回避し、信頼性の高いAI活用を実現するための戦略は、2025年以降の企業成長において最も重要な要素の一つとなるでしょう。


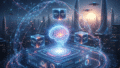
コメント