はじめに
2022年11月のChatGPT登場以来、生成AIは私たちのビジネスや日常生活に急速に浸透し、その活用はもはや無視できないものとなっています。企業における生産性向上、新たなサービス開発、業務効率化など、多岐にわたる分野で生成AIの可能性が探求されており、その進化はとどまることを知りません。しかし、その一方で、技術の急速な発展に追いつくための知識習得や、倫理的・法的な課題への対応も喫緊の課題となっています。
このような背景から、生成AIに関する学習ニーズは高まる一方です。多くの企業が従業員のスキルアップを図るため、また個人も自身のキャリア形成のために、生成AIの基礎から応用までを体系的に学べる機会を求めています。今回は、こうした学習ニーズに応えるべく、2025年10月に新規開講されるeラーニングコースに焦点を当て、その内容と、企業および個人にとっての価値を深掘りして解説します。
生成AI学習のニーズの高まりと現状
生成AIの普及に伴い、その活用は多様な場面で見られるようになりました。例えば、20代の転職希望者の半数近くが転職活動で生成AIを利用しており、「自己PR作成・添削」が最も多い活用方法として挙げられています。これは、生成AIが個人の業務やキャリア形成に直結するツールとして認識されていることを示しています。(参考:20代転職希望者の半数近くが「転職活動で生成AIを利用」。「自己PR作成・添削」が最多。応募書類・面接対策・企業研究など様々な場面で活用)
一方で、企業における生成AIの導入にはまだ課題も多く存在します。MM総研の調査によると、生成AIの認知度は2025年8月時点で80.4%に達しているものの、利用経験は20%強に留まっており、特に「ChatGPT」が最多のサービスとなっています。(参考:生成AIの利用経験は20%強 サービス別は「ChatGPT」が最多) 導入が進まない理由としては、情報漏洩リスクへの懸念、適切な利用ルールの不在、そして従業員のスキル不足などが挙げられます。企業が生成AIを導入し、成果を出すためには、技術的な理解だけでなく、組織全体の意識改革や適切なガバナンス体制の構築が不可欠です。
このような状況において、体系的な学習機会の提供は、生成AIの本格的な社会実装を促進する上で極めて重要な役割を担います。単なるツールの使い方だけでなく、その仕組みや業務への適用方法、さらには潜在的なリスクへの対処法までを網羅的に学ぶことが求められているのです。
注目イベント:日本能率協会マネジメントセンター「eラーニングライブラリ®」新規5コース開講
株式会社日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)は、2025年10月に、企業の人材育成を支援する「eラーニングライブラリ®」において、生成AIに関する基礎知識を学べるコースを含む新規5コースを開講します。特に注目すべきは、「生成AIに関する基礎知識」コースです。
- イベント名: 「eラーニングライブラリ®」生成AIに関する基礎知識を学べるコース
- 実施日付: 2025年10月 新規開講
- 主催: 株式会社日本能率協会マネジメントセンター
- 形式: eラーニング(オンライン学習)
- 詳細URL: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000417.000082530.html
このコースは、生成AIを初めて活用するビジネスパーソンを主な対象としています。単にツールの操作方法を教えるだけでなく、生成AIがどのような仕組みで動作するのか、そして業務で効果的に使いこなすためのポイントは何かを体系的に学ぶことを目的としています。受講者は、生成AIの基本的な操作方法を理解し、業務に役立つ簡単な指示(プロンプト)を出せるようになることを目指します。
このコースは「イベント」というよりは「学習コンテンツの提供開始」という性質を持ちますが、生成AIの基礎を体系的に学ぶための重要な機会であり、「勉強会」の広範な解釈として、多くのビジネスパーソンが生成AIの知識を習得するための第一歩となるでしょう。
「生成AIに関する基礎知識」コースの具体的な内容と学習効果
このコースでは、生成AIの理解と活用に必要な要素が網羅されています。具体的な学習内容は以下の点が中心となると考えられます。
- 生成AIの基本概念と仕組み:
生成AIとは何か、どのような技術的背景に基づいて動作するのかを解説します。大規模言語モデル(LLM)の基本的な構造や、学習データの役割など、技術的な側面を分かりやすく学ぶことで、生成AIが「魔法の鏡」のように見える理由を深く理解できるでしょう。(参考:生成AIという「魔法の鏡」をビジネスリーダーはいかに活用すべきか⁉ 脳科学者・茂木健一郎が徹底解説 挑戦をサポートする「次代への一手」)
- プロンプトエンジニアリングの基礎:
生成AIから望む出力を得るためには、適切な指示(プロンプト)を与えるスキルが不可欠です。本コースでは、効果的なプロンプトの作成方法や、試行錯誤を通じて精度を高めるための基本的な考え方を習得します。これにより、受講者は業務における具体的な課題解決に生成AIを活用する第一歩を踏み出せるようになります。
- 生成AIの業務活用事例と応用:
単なる知識だけでなく、実際の業務でどのように生成AIを活用できるのか、具体的な事例を交えて紹介されます。資料作成、アイデア出し、情報収集、コンテンツ生成など、様々な業務シーンでの応用方法を学ぶことで、自身の業務に生成AIを組み込むイメージを具体化できます。これは、AIポータルメディア「AIsmiley」が公開した「生成AIの部署別ユースケース15選」のような実践的な視点と共通するものです。(参考:明日から業務が変わる!生成AI活用の実践アイデア集「生成AIの部署別ユースケース15選」を公開!)
- 生成AI利用におけるリスクと倫理:
生成AIの活用には、情報漏洩や著作権侵害、ハルシネーション(虚偽情報の生成)といったリスクが伴います。本コースでは、これらのリスクを認識し、適切に対処するための基本的な考え方も提供されるでしょう。これは、企業が生成AIを安全に導入・運用するために不可欠な知識であり、生成AIの情報漏洩リスク対策や情シス向けリスク管理セミナーなどでも強調される重要なテーマです。
このeラーニングコースを通じて、受講者は生成AIの基本的なリテラシーを習得し、業務効率化や新たな価値創造に貢献できる土台を築くことができます。特に、生成AIに初めて触れる層にとっては、安心して学習を始められる最適な機会となるでしょう。
このコースが提供する価値
日本能率協会マネジメントセンターの「eラーニングライブラリ®」は、企業の人材育成を長年支援してきた実績があります。今回の生成AIコースは、そのノウハウが凝縮されており、企業や個人にとって以下のような多大な価値を提供します。
企業にとっての価値
- 従業員のAIリテラシー向上:
全従業員が生成AIの基礎を理解することで、組織全体のAIリテラシーが底上げされます。これにより、部門横断的なAI活用プロジェクトが推進しやすくなり、生成AIを企業文化に定着させるための重要な一歩となります。
- 業務効率化と生産性向上:
生成AIの正しい使い方を学ぶことで、従業員は日常業務における非効率なプロセスを見直し、AIを活用した効率化を実現できます。例えば、資料作成やメールの下書きなど、様々なタスクで生成AIの恩恵を受けることが可能です。(参考:生成AI Google Opal ノーコードでAIエージェントを作ってみよう|ひつじ|AIをわかりやすく)
- リスク管理とガバナンス強化:
情報漏洩リスクや倫理的課題に対する意識を高めることで、企業は生成AIの安全な利用環境を構築しやすくなります。これは、生成AIプロジェクト成功への道において不可欠な要素です。
- 人材育成コストの最適化:
eラーニング形式であるため、時間や場所を選ばずに学習を進めることができ、集合研修に比べてコストを抑えながら多くの従業員に学習機会を提供できます。特に、みずほフィナンシャルグループのように、生成AI活用を重要な経営課題と定め、従業員の不安解消に取り組む企業にとって、このような学習機会は非常に有効です。(参考:生成AIに仕事を取って代わられる? 従業員の不安感、みずほFGはどう解消するのか 上ノ山CDOに聞く)
個人にとっての価値
- キャリアアップと市場価値向上:
生成AIのスキルは、現代のビジネスシーンで非常に高く評価されます。このコースで基礎を固めることで、自身の市場価値を高め、キャリアアップの機会を広げることができます。
- 仕事の幅と創造性の拡大:
生成AIを使いこなすことで、ルーティンワークから解放され、より創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになります。これにより、仕事の満足度向上にも繋がるでしょう。
- 最新技術への対応力強化:
生成AIは進化のスピードが速い技術です。基礎知識を習得することで、今後登場する新たなAI技術やサービスにも柔軟に対応できる土台を築けます。
生成AI学習の今後と展望
生成AIは、すでに私たちの社会に深く根付き始めており、その影響は今後さらに拡大していくでしょう。企業が生成AIを真に競争優位性として活用するためには、技術の導入だけでなく、従業員一人ひとりのスキル向上と、組織文化としてのAI活用推進が不可欠です。日本能率協会マネジメントセンターのような信頼できる機関が提供するeラーニングコースは、こうした学習ニーズに応え、企業と個人の両面から生成AIの健全な発展を支える重要なインフラとなります。
今後は、基礎知識に加えて、特定の業務領域に特化した生成AI活用術や、AIエージェントの構築・運用に関する実践的な内容など、より専門性の高い学習コンテンツの需要も高まることが予想されます。継続的な学習と情報収集を通じて、生成AIがもたらす変革の波を乗りこなし、新たな価値を創造していくことが求められます。
まとめ
2025年10月に日本能率協会マネジメントセンターが開講する「eラーニングライブラリ®」の「生成AIに関する基礎知識」コースは、生成AIの急速な普及とビジネス活用の高まりの中で、企業と個人がその恩恵を最大限に享受するための重要な学習機会です。生成AIの仕組みから業務への応用、そしてリスク管理までを体系的に学ぶことで、受講者はAIリテラシーを高め、業務効率化や新たな価値創造に貢献できるスキルを身につけることができます。
生成AIの導入には「嫌われる勇気」が必要だと言われるほど、組織変革を伴うものです。(参考:生成AI導入に必要なのは「嫌われる勇気」──“オレ流”で貫く、組織改革のススメ) このコースは、その変革を円滑に進めるための基盤となる知識を提供し、企業が生成AIを戦略的に活用し、未来の競争力を高めるための一助となることでしょう。この機会を活用し、生成AI時代のビジネスをリードする人材へと成長していくことを期待します。
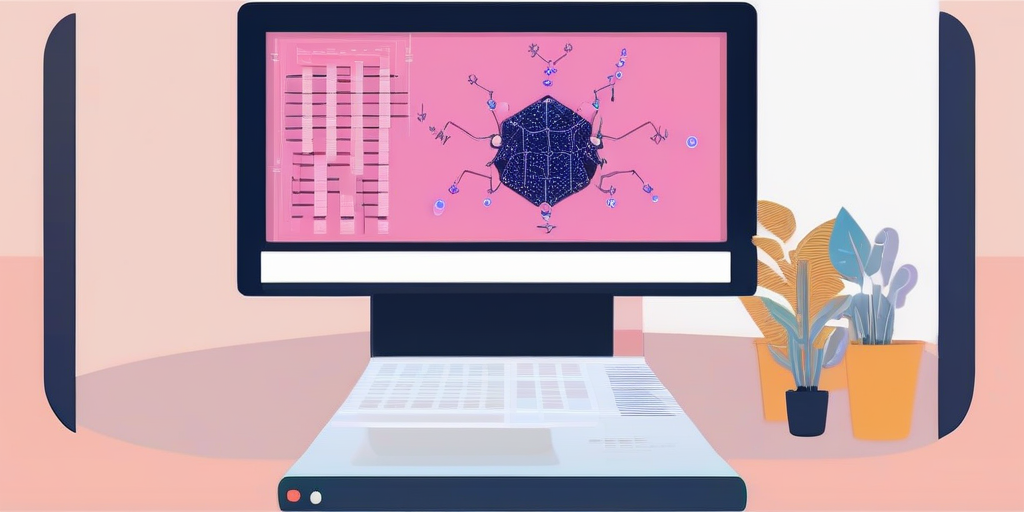
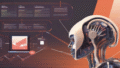
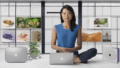
コメント