はじめに
2025年、生成AI技術はビジネスのあらゆる側面に浸透し、その進化はとどまることを知りません。テキスト、画像、音声、動画といった多種多様なコンテンツを瞬時に生成する能力は、すでに多くの企業の業務効率化や新たな価値創造に貢献しています。しかし、その次のステージとして注目されているのが「AIエージェント」です。単にコンテンツを生成するだけでなく、自律的に目標を設定し、計画を立て、ツールを使いこなし、タスクを遂行するAIエージェントは、生成AIの可能性をさらに広げ、企業のオペレーションを根本から変革する潜在力を秘めています。
ガートナージャパンが発表した「2025年の日本における未来志向型インフラテクノロジーのハイプ・サイクル」では、生成AIがすでに「幻滅期」に入りつつある一方で、AIエージェントは「過度な期待のピーク」に位置付けられています。これは、生成AIが実用段階に入り、その限界と課題が認識され始めた結果、より高度な自律性を持つAIエージェントへの期待が高まっていることを示唆しています。(参照:生成AIは幻滅期、AIエージェントは「過度な期待」のピーク ガートナー「未来志向型インフラテクノロジーのハイプ・サイクル」)
本稿では、このAIエージェントに焦点を当て、特に企業におけるAIエージェントの内製化・カスタマイズの動向とその実践的な導入アプローチについて深掘りします。単なる技術解説に留まらず、具体的な企業の取り組み事例や、導入におけるメリット・課題、そして今後の展望までを包括的に議論することで、読者の皆様がAIエージェントの真の価値を理解し、自社のビジネスに活かすための示唆を提供します。
AIエージェントとは何か:生成AIとの違いと進化
生成AIとAIエージェントは密接に関連していますが、その機能と役割には明確な違いがあります。生成AI、特に大規模言語モデル(LLM)は、与えられたプロンプトに基づいてテキスト、画像、コードなどを「生成」することに特化しています。これは強力な能力ですが、多くの場合、人間の指示なしには一連の複雑なタスクを自律的に遂行することはできません。
これに対し、AIエージェントは、単一の生成タスクを超え、より広範な目標達成に向けて自律的に行動する能力を持ちます。その主要な特徴は以下の通りです。
- 自律性(Autonomy):人間からの継続的な指示なしに、自身の判断で行動を決定し、実行する能力。
- 計画性(Planning):複雑な目標を達成するために、複数のステップに分解し、実行計画を立てる能力。
- ツール利用(Tool Use):外部のAPI、データベース、ウェブ検索、他のソフトウェアツールなどを利用して、自身の能力を拡張する能力。
- 記憶(Memory):過去の対話や行動履歴を記憶し、それを将来の意思決定に活かす能力。
AIエージェントは、これらの要素を組み合わせることで、例えば「特定のテーマに関するレポートを作成する」という目標に対して、自律的に情報収集を行い(ウェブ検索ツールを利用)、得られた情報を分析・要約し(LLMを利用)、レポートの構成を計画し、最終的なドラフトを生成するといった一連のプロセスを遂行できるようになります。これは、単にテキストを生成するだけの生成AIとは一線を画す、より高度な機能と言えるでしょう。
このようなAIエージェントの進化は、生成AIが情報空間に革命をもたらした次の段階として、現実の物理世界や複雑なビジネスプロセスに触れる力を獲得しようとしていることを示しています。日経ビジネス電子版の記事でも、「生成AI(人工知能)というかAIエージェントはDX(デジタルトランスフォーメーション)の最強のツールだ。なんせ、これまで登場したどのIT/デジタルツールと比べても破壊力抜群なんでね。」と述べられており、その破壊的な可能性が強調されています。(参照:経営陣が生成AIだけに夢中な会社は滅びる AIエージェントでDX推進:日経ビジネス電子版)
AIエージェントの概念については、以前の記事でも解説しています。AIの次なる進化:マルチエージェントAIが拓く未来と主要プレイヤーの戦略や、AIエージェントが拓くビジネス変革:生成AIのパラドックスを乗り越えるもご参照ください。
企業におけるAIエージェント導入の動向
2025年現在、企業によるAIエージェントの導入は、特定の業務プロセスの自動化や最適化を目指す具体的な動きとして顕在化しています。特に注目すべきは、自社業務に特化したAIエージェントの内製化やカスタマイズを進める動きです。
システム開発の上流工程を半自動化する電通総研の事例
株式会社電通総研は、システム開発の上流工程を半自動化する独自のAIエージェントを開発し、本格運用を開始しました。このAIエージェントは、要件定義や基本設計といったシステム開発の初期段階において、生成AIを活用してドキュメント作成や分析作業を支援します。これにより、開発期間の短縮や品質向上が期待されています。
テクノロジーで企業と社会の進化を実現する株式会社電通総研(本社:東京都港区、代表取締役社長:岩本 浩久、以下「電通総研」)は、生成AIでシステム開発の上流工程を半自動化する独自のAIエージェントを開発し、本格運用を開始しました。
この事例は、AIエージェントが単調な作業だけでなく、高度な知識と判断が求められる業務においても、人間の専門家を支援し、生産性を向上させる可能性を示しています。特に、システム開発の上流工程は、プロジェクト全体の成否を左右する重要なフェーズであり、そこでのAIエージェント活用は大きなインパクトを持つでしょう。
開発支援としてのAIエージェント活用:エムスリーテックブログの振り返り
エムスリーテックブログでは、「ほどほどに使う生成 AI」と題し、開発支援としてAIエージェントを活用した経験が共有されています。記事では、AIエージェントが開発プロセスにおいてどのような役割を果たし、どのような課題があったのかが具体的に振り返られています。
この記事はコンシューマーチーブログリレー4日目の記事です。 エムスリーエンジニアリングG コンシューマーチームの松原です。 今回はここ半年ほど開発支援として使っていた AI エージェントについて振り返ります。
この事例は、AIエージェントが実務の現場でどのように受け入れられ、どのような調整が必要となるのか、具体的な知見を提供します。開発支援ツールとしてのAIエージェントは、コード生成、デバッグ、ドキュメント作成など多岐にわたるタスクで活用され、開発者の生産性向上に寄与することが期待されます。しかし、同時に過度な期待をせず、人間の判断と協調しながら「ほどほどに使う」ことの重要性も示唆しています。
ノーコードでのAIエージェント構築支援:株式会社ALLIの事例
AIエージェントの導入を加速させる動きとして、ノーコードでAIエージェントを構築できるサービスも登場しています。株式会社ALLIは、「マナビトエージェントfor biz」をリリースし、15時間の講師付き研修を通じて、企業がオリジナルのAIエージェントをノーコードで構築できるよう支援しています。
生成AIの登場以降、AIエージェントによる業務自動化の開発コストが下がったことで、AIエージェントの導入がより身近なものになりました。株式会社ALLIは、この流れを受け、企業が独自にAIエージェントを構築・運用できるよう、ノーコードプラットフォームと研修プログラムを提供しています。
ノーコードでのAIエージェント構築は、専門的なプログラミング知識がない企業でも、業務に特化したAIエージェントを迅速に導入できるという大きなメリットがあります。これにより、AIエージェントの活用は特定のIT部門だけでなく、営業、マーケティング、人事など、より幅広い部門へと広がる可能性を秘めています。
Google Cloud「Gemini Enterprise」の統合戦略
大手テクノロジー企業も、企業向けAIエージェントの基盤強化に注力しています。Googleは、企業向けのAI基盤「Gemini Enterprise」を発表し、これまで個別に提供されてきたAI関連のツールやモデルを単一のプラットフォームに統合しました。
米Google(グーグル)は、ビジネス向けのAI基盤「Gemini Enterprise」を発表した。「Gemini Enterprise 」は、GeminiをベースとしたAIモデルで、チャット機能だけでなく、企業データとの連携やセキュリティ、管理機能が強化されている。
この統合プラットフォームは、企業が業務のあらゆる場面でAIエージェントを容易に活用できるよう設計されています。既存のビジネスアプリケーションとの連携を強化し、カスタマイズ可能なAIモデルを提供することで、企業は自社のニーズに合わせたAIエージェントを構築しやすくなります。これは、MicrosoftのCopilotやOpenAIのChatGPT Enterpriseなど、競合他社の企業向けAIサービスに対抗するGoogleの戦略の一環でもあります。
こうしたプラットフォームの進化は、企業がAIエージェントを内製化・カスタマイズする際の基盤として、重要な役割を果たすでしょう。クラウドAIプラットフォームを活用した企業特化型AIモデルの構築については、企業特化型生成AIモデル:クラウドAIプラットフォーム活用の開発・運用と未来でも詳しく議論しています。
AIエージェント内製化・カスタマイズのメリットと課題
企業がAIエージェントを内製化またはカスタマイズする際には、多くのメリットがある一方で、無視できない課題も存在します。
メリット
-
業務特化と精度向上:
汎用的なAIエージェントでは対応しきれない、企業固有の複雑な業務プロセスや専門知識に特化したエージェントを構築できます。これにより、特定の業務における自動化の精度と効率が飛躍的に向上します。例えば、電通総研の事例のように、システム開発の上流工程といった専門性の高い領域での支援が可能になります。
-
セキュリティとデータガバナンス:
機密性の高い企業データを外部サービスに依存することなく、自社の管理下でAIエージェントを運用できます。これにより、情報漏洩のリスクを最小限に抑え、厳格なデータガバナンスを確立することが可能です。特に金融や医療など、規制の厳しい業界ではこの点が重要となります。生成AIの情報漏洩リスク対策:独自開発、セキュアサービス、RAGを解説も参照ください。
-
競争優位性の確立:
自社独自のノウハウや企業文化を反映したAIエージェントは、競合他社にはない独自の強みとなり得ます。これにより、市場での差別化を図り、新たなビジネスモデルやサービスを創出する競争優位性を確立できます。
-
コスト最適化と柔軟性:
長期的に見れば、外部サービスへの継続的な依存を減らし、運用コストを最適化できる可能性があります。また、自社で開発・運用することで、ビジネス環境の変化に合わせた機能追加や改善を柔軟に行うことができます。
課題
-
技術的ハードルと専門人材の不足:
AIエージェントの内製化には、LLMに関する深い知識、プログラミングスキル、データエンジニアリングの専門知識が必要です。多くの企業にとって、これらの専門人材の確保や育成は大きな課題となります。エムスリーテックブログの事例のように、実践的な知見を蓄積する過程も必要です。
-
データ管理と品質確保:
AIエージェントの性能は、学習データの質に大きく依存します。適切で偏りのない高品質なデータを大量に準備し、継続的に管理・更新していく体制が必要です。データの収集、前処理、アノテーションといった作業は、時間とコストがかかります。
-
倫理的・ガバナンス上の問題:
AIエージェントの自律性が高まるにつれて、倫理的な問題や責任の所在が曖昧になるリスクが増大します。誤った判断を下した場合の責任、バイアス、プライバシー侵害など、多岐にわたる課題に対する明確なガイドラインとガバナンス体制の構築が不可欠です。
-
初期投資と運用負荷:
AIエージェントの開発・導入には、GPUなどのハードウェア、開発ツール、クラウドサービスへの初期投資が必要です。また、導入後もモデルの監視、メンテナンス、アップデートといった運用負荷が発生します。
企業が独自にAIモデルを構築することの重要性については、企業独自生成AIモデル構築の重要性:2025年以降のビジネス展望を解説でも触れています。
AIエージェント導入成功のための実践的アプローチ
AIエージェントの内製化・カスタマイズは、多くの企業にとって挑戦的な取り組みですが、以下の実践的アプローチにより、成功への道を切り開くことができます。
スモールスタートと段階的導入
最初から大規模なシステムを構築しようとせず、小規模なパイロットプロジェクトから始めることが重要です。特定の業務プロセスに絞り、限定的な範囲でAIエージェントを導入し、その効果と課題を検証します。成功体験を積み重ねながら、徐々に適用範囲を広げていくことで、リスクを抑えつつ、組織全体でのAIエージェント活用を推進できます。例えば、まずは特定の部署のデータ分析支援や、問い合わせ対応の一部自動化から始めるなどが考えられます。
生成AIの企業活用におけるスモールスタートの重要性については、【イベント】生成AI企業活用の始め方:10/28開催ウェビナーで学ぶ成功戦略:スモールスタートとはでも議論されています。
ノーコード/ローコードツールの活用と人材育成
前述の株式会社ALLIの事例のように、ノーコード/ローコードでAIエージェントを構築できるプラットフォームの活用は、技術的ハードルを下げる有効な手段です。これにより、IT部門以外の現場の従業員でも、自身の業務知識を活かしてAIエージェントの開発に携わることが可能になります。同時に、AIリテラシー教育やプロンプトエンジニアリングの研修などを通じて、全社的なAI活用能力の底上げを図ることも不可欠です。
リスク管理と倫理ガイドラインの策定
AIエージェントの自律性が高まるほど、予期せぬ挙動や倫理的問題が発生するリスクも高まります。導入前から、情報漏洩対策、バイアスチェック、誤情報の生成防止策など、具体的なリスク管理体制を構築する必要があります。また、AIの利用目的、責任の所在、人間の監視体制などを明確化した社内ガイドラインを策定し、従業員への周知徹底を図ることが重要です。デジタル庁の「AI班」の活動のように、行政機関でもガバメントAI構築に向けた取り組みが進められています。(参照:【代替テキスト】【AIアプリを内製開発!?】行政の未来を切り開く!「AI班」の活動の裏側に密着【ガバメントAI構築へ】|デジタル庁ニュース)
既存システムとの連携強化
AIエージェントが最大の効果を発揮するためには、既存の基幹システムやデータベース、SaaSアプリケーションとのシームレスな連携が不可欠です。API連携やRAG(Retrieval Augmented Generation)といった技術を活用し、AIエージェントが企業の持つ豊富なデータを参照し、活用できる環境を構築することが重要です。Google CloudのGemini Enterpriseのような統合プラットフォームは、このような連携を容易にするでしょう。
2025年以降のAIエージェントの展望
2025年以降、AIエージェントはさらに進化し、ビジネスと社会に大きな変革をもたらすことが予想されます。
物理世界への進出とロボットとの融合
現在のAIエージェントの多くは、情報空間でのタスク遂行に特化していますが、次の大きな潮流は物理世界との融合です。プレジデントオンラインの記事では、「チャットGPTに象徴される生成AIは、知識や言語といった『情報空間』に革命を起こした。しかし、現実の物理世界に触れる力は持たなかった。社会が次に求めるのは、…ロボットが来る!」と指摘されています。(参照:「生成AIの次」はロボットが来る! 7400兆円市場で日本企業が勝つ方法 田中道昭のビジネスニュース最前線)
AIエージェントがロボットと融合することで、工場での生産、物流、介護、災害対応など、物理的な作業を自律的に行うヒューマノイドロボットや産業用ロボットが普及する可能性があります。これは、AIエージェントが単なるソフトウェアの枠を超え、現実世界で行動する「実体」を持つことを意味し、その応用範囲は計り知れません。物理世界と融合するAIエージェントについては、以前の記事物理世界と融合するAIエージェント:技術進化、応用、日本企業の戦略でも詳しく解説しています。
業界横断的な応用拡大
AIエージェントは、特定の業界や業務に限定されず、あらゆる分野での応用が拡大するでしょう。例えば、金融業界ではパーソナライズされた投資アドバイスや不正検知、医療業界では診断支援や新薬開発の加速、小売業界では顧客対応の自動化や在庫管理の最適化などが考えられます。すでに「生成AIによる相続・財産承継提案システム」の開発計画が進行中であり、2026年1月からの本格販売を目指しています。(参照:「生成AIによる相続・財産承継提案システム」の開発計画について)これは、高度な専門知識を要する分野におけるAIエージェント活用の具体例と言えるでしょう。
人間とAIエージェントの協調
AIエージェントの進化は、人間の仕事を奪うものではなく、人間の能力を拡張し、より創造的で価値の高い仕事に集中できる環境をもたらすでしょう。人間とAIエージェントがそれぞれの強みを活かし、協調しながら働く「ヒューマン・イン・ザ・ループ」のモデルが主流となると考えられます。AIエージェントがルーティンワークや情報収集、計画立案の大部分を担い、人間は最終的な意思決定、倫理的判断、創造的な発想、感情的なコミュニケーションといった、より高度な役割を果たすようになるでしょう。
自律AIエージェントが変えるビジネスと開発への影響については、Claude Sonnet 4.5の衝撃:自律AIエージェントが変える未来:ビジネスと開発への影響もご参考ください。
まとめ
2025年、生成AI技術はAIエージェントへとその進化の軸足を移しつつあります。単なるコンテンツ生成に留まらず、自律的に目標を達成する能力を持つAIエージェントは、企業における業務自動化、効率化、そして新たな価値創造の可能性を大きく広げています。
電通総研によるシステム開発の上流工程半自動化、エムスリーテックブログでの開発支援としての活用、そして株式会社ALLIによるノーコード構築支援サービスの登場は、企業がAIエージェントを内製化・カスタマイズし、自社のニーズに最適化していく具体的な動きを示しています。また、Google Cloudの「Gemini Enterprise」のような統合プラットフォームは、その導入を加速させる基盤となるでしょう。
AIエージェントの内製化・カスタマイズは、業務特化による精度向上、セキュリティ強化、競争優位性の確立といったメリットをもたらします。一方で、技術的ハードル、専門人材の不足、データ管理、倫理的課題といった克服すべき障壁も存在します。これらの課題に対しては、スモールスタート、ノーコード/ローコードツールの活用、人材育成、リスク管理と倫理ガイドラインの策定、既存システムとの連携強化といった実践的なアプローチが有効です。
今後、AIエージェントは物理世界へと進出し、ロボットとの融合を通じてその応用範囲を飛躍的に拡大するでしょう。そして、人間とAIエージェントが協調する新たな働き方が定着し、企業の生産性と創造性は未曾有のレベルに到達すると考えられます。企業は今、このAIエージェントの潮流を正確に捉え、積極的にその導入と活用を進めることで、未来の競争力を確保する重要な局面に立たされています。


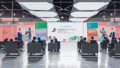
コメント